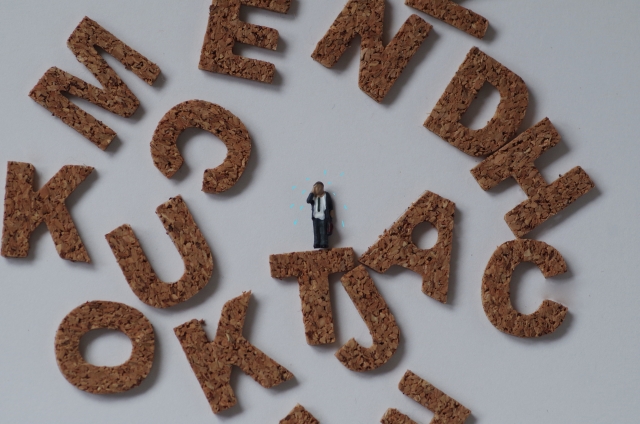世界に研究成果を発信し、世界中の研究者とアイディアを共有するためには、論文を英語で執筆することが不可欠です。
しかし、英語論文に苦手意識を感じている研究者の方も多いでしょう。正しい文法が求められるだけでなく、論理的な構成や、英語論文独特の言い回しが必要になるからです。
この記事では、英語の基本的な書き方や、読みやすい論文・説得力のある論文を書くコツを紹介します。
英語論文の基本構成
それでは、英語で論文を書く際の基本的な構成を見ていきましょう。
英語論文はIMRaDフォーマットに沿って書くと効果的
英語論文を書く際には、「IMRaDフォーマット」をおさえておきましょう。IMRaDとは「Introduction, Methods, Results, and Discussion」の略です。
IMRaDフォーマットは、多くの学術論文で採用されている一般的な構成で、論理的かつ明確に研究内容を伝えるために設計されています。
序論(Intriduction)では、研究の背景や目的、問題提起を行います。
方法(Methods)では、研究の進め方や実験の方法・データ収集の方法を説明します。
結果(Results)では、自信の研究が発見した成果と、具体的なデータを明らかにします。
議論(Discussion)では、結果の解釈とその意義について述べます。
それでは、英語論文の基本的な構成を、具体的な例文とともに見ていきましょう。
英語論文の一般的な構成
英語論文の一般的な構成は、以下の通りです。
概要から始め、IMRaDフォーマットの流れを経て、結論を述べます。
- 概要(Abstract)
- 序論(Introduction)
- 方法(Methods)
- 結果(Results)
- 議論(Discussion)
- 結論(Conclusion)
概要(Abstract)
英語論文では、本論に入る前に、研究の概要を100〜250語程度でまとめて掲載します。
概要には、研究の背景、目的、方法、主な結果、結論についての情報をすべて含める必要があります。
例えば、海洋科学に関する論文であれば、以下のような内容になります。
本研究は、気候変動が太平洋の海洋生物多様性に与える影響を調査するものである。衛星データと生態学的調査を用いて、過去20年間の種の分布変化を分析した。その結果、特にサンゴ礁生態系において著しい変化が見られた。これらの結果は、早急な保全戦略の必要性を示唆している。
序論(Introduction)
本文は、序論(Introduction)から始めます。序論では、研究の背景を説明し、問題を提起し、研究の目的を述べます。
以下が典型的な流れです。
- 背景(なぜこの研究が重要なのか)
- 問題提起(何を明らかにすべきか)
- 目的(この研究が何を明らかにしたのか)
先ほどの「気候変動が海の生物多様性に与える影響」を例にとると、以下のようになります。
- Climate change has been significantly affecting marine ecosystems.
気候変動は海洋生態系に大きな影響を与えている。
- However, the long-term effects on species distribution remain unclear.
しかし、種の分布に対する長期的な影響については、まだ不明な点が多い。
- This study aims to analyze changes in biodiversity patterns using satellite data.
この研究は、衛星データを用いて生物多様性のパターンの変化を分析することを目的としている。
方法(Methods)
方法(Methods)では、研究の手法やデータの収集方法を説明します。
実験・調査の方法や、統計解析の方法について網羅的に情報を記載し、再現性を確保しましょう。
具体的には、研究対象(どのデータ・サンプルを使ったか)、手法(実験や分析の具体的な手順)、統計処理(どのようなデータ解析を行ったか)を記載します。
例えば、以下のような表現を使います。
2000年から2020年までの衛星画像を収集し、機械学習モデルを用いて気温変動を分析した。統計解析にはソフトウェアAを使用した。
結果(Results)
結果(Results)では、研究の主な結果をデータとともに示します。
図や表を用いて、視覚的に分かりやすくするのがポイントです。
結果の項では、データの傾向を客観的に述べましょう。解釈・考察は議論(Discussion)の項で行います。
また、想定と違った結果であっても、隠さずに記述しましょう。
具体的には、以下のような表現が使えます。
分析の結果、海水温の有意な上昇(p < 0.05)が明らかになり、それに伴って種の分布もより低温の地域へとシフトした。
議論(Discussion)
議論(Discussion)の項では、結果の解釈と、その意義を説明します。
今後の課題についてもこの項で述べましょう。
基本的な流れは、以下のようなものになります。
- 主な研究結果の解釈
- 先行研究との比較
- 今後の課題
具体的な例文としては、以下を参考にしてください。
- Our findings suggest that rising sea temperatures are driving species migration.
今回の発見は、海水温の上昇が種の移動を促していることを示唆している。 - These results align with previous studies on coral bleaching.
これらの結果は、サンゴの白化に関する先行研究と一致している。 - Further research is needed to examine long-term adaptation mechanisms.
長期的な適応メカニズムを検討するためには、さらなる研究が必要である。
結論(Conclusion)
英語論文の最後は、結論(Conclusion)で研究の主要なポイントを簡潔にまとめましょう。
将来の研究の方向性なども付け加えると効果的です。
具体的には、以下のようなフレーズが使えます。
この研究は、気候変動が海洋生物多様性に与える影響を浮き彫りにしている。今後の研究では、これらの影響を緩和するための保全戦略を探る必要がある。
英語論文を書くときのポイント
英語論文を書く時は、以下のポイントに気を付けましょう。
- 能動態を積極的に使う
- 時制に気を付ける
- 接続詞を活用する
能動態を積極的に使う
日本語で論文を書く際は「〜と考えられる」「〜と思われる」と、受動態が好まれますよね。
しかし、英語の学術論文では受動態より能動態が好まれることが多く、NatureやScienceなどの科学雑誌でも、能動態が推奨されています。
「We conducted an experiment to analyze the data.(能動態)」という文の方が、「An experiment was conducted to analyze the data.(受動態)」よりも明確で簡潔な印象ですよね。
ただし、実験手法や客観的な処理を説明する時は、受動態がふさわしい場合もあります。
サンプルはスペクトロメーターで分析された。
データは100人の参加者から収集された。
方法(Method)のパートでは受動態がふさわしい場合もありますが、序論(Introduction)・議論(Discussion)・結果(Conclusion)のパートでは能動態を使うことで、説得力を増すことができます。
時制に気を付ける
英語論文を書く際は、学術誌に応募して査読を受けるケースがほとんどでしょう。
論文査読の際は、英語力も重視されます。
最終的には英文校正ツールを使ったり、ネイティブによる校正を受けることがほとんどかと思いますが、自分で英文を書く段階でも、時制に気を付けましょう。
一般論や既存の事実をいう場合は、現在形を使います。
水は100度で沸騰する。
気候変動は海洋生物に影響を与える。
その一方で、自分の研究の方法・結果や結果については、過去形がふさわしいことが多いです。
私たちは100のサンプルを分析した。
気温は2度上昇した。
そして結論や主張には現在形を使うと効果的です。
この研究は…を示している。
この結果は、海洋の温暖化が加速していることを示唆している。
接続詞を活用する
英語論文を書く時は、接続詞を活用することで、話の流れが分かりやすくなり、より効果的にメッセージを伝えることができます。
以下に、英語論文を書く上で押さえておきたい接続詞を挙げます。
追加:Furthermore, Moreover, In addition
対比:However, On the other hand, In contrast
原因・結果:Therefore, Thus, Consequently
例示:For example, Such as, Namely
結論:In conclusion, To summarize
英語論文を書く際に役立つツール
ここでは、英語論文を書く際に役立つツールを紹介します。
英語論文を書く際は、英文の構成・文法チェックをしてくれるツールや、参考文献の管理をしてくれるツールが役立ちます。
英文校正・文法チェックツール
英文校正・文法チェックツールとして代表的なものとしては、以下のツールが挙げられます。
- Grammarly
- DeepL Write
- Hemingway Editor
- Trinka AI
Grammarlyは、文法・語彙をチェックしてくれるツールで、AIがリアルタイムで修正を提案してくれます。
DeepL Writeは、英文を自然な表現へと調整してくれます。
Hemindway Editorは、簡潔な文章作成をサポートしてくれるので、冗長表現を削るのに最適です。
Trinka AIは、最も学術論文向けの校正ツールといえますが、有料サービスなので、英語論文を書く頻度が高い方におすすめです。
そして、これらのツールは、完璧に英語を添削してくれるわけではないので、最終的には、外部機関のネイティブによるチェックサービスの利用をおすすめします。
参考文献管理ツール
研究論文を書く際には、多くの論文や書籍を引用するため、参考文献の管理も重要になってきますよね。
ただ、手作業で整理すると、時間がかかるだけでなく、脚注などのミスも起こりやすくなります。そこで便利なのが、参考文献管理ツール です。
脚注管理ツールとして代表的なのは、以下の3つのツールです。
- Zotero(ゾテロ)
- Mendeley(メンデレー)
- EndNote(エンドノート)
Zotero は、無料で利用できるオープンソースの文献管理ツールです。シンプルで使いやすいため、英語論文を書き始めた方におすすめです。
Mendeleyは、PDFに直接注釈をつけられるのが特徴です。
EndNoteは大規模な文献管理に適したツールです。
ZoteroとMendeleyは基本的に無料で利用することができますが、無料版のストレージには限りがあります。
EndNoteは有料版のみ提供されているので、英語論文を書く頻度が高い方に向いたツールといえます。
英語論文の査読を受ける際の注意
英語論文を書いたら、学術雑誌に応募し、査読を受けることになりますよね。
査読を受けるからには、リジェクト(却下)を回避し、無事学術誌に掲載されたいものです。
査読を受ける際に論文がリジェクトされる理由としては、主に以下の3つが挙げられます。
- 論理構成がおかしい
- 研究に独自性がない
- 英語レベルが低い
そしてリジェクトを防ぐコツは、以下の7つです。
- ジャーナルの研究対象に合った投稿先を選ぶ
- IMRaD構成を徹底し、論理的な流れを明確にする
- 文法・英語表現をチェックし、読みやすくする
- 研究の独自性と意義を強調する
- 適切な参考文献を選び、引用ミスを防ぐ
- 事前にプレ査読を受け、フィードバックを活用する
- 査読コメントには論理的かつ丁寧に対応する
まず、リジェクトされる大きな理由の1つは、「ジャーナルの研究対象(スコープ)に合わないこと」です。
ジャーナルの「Aims and Scope」を必ず確認し、研究の規模に適したジャーナルを選びましょう。
過去の掲載論文をチェックするのも効果的です。
2・3の対策については、前の章で解説した通りです。
そして、査読者は「この研究が何を新しく明らかにしたのか?」を重視します。
Introductionでは独自性を明確に記述しましょう。
過去の研究と比較し、実験データや解析方法が新規であると強調する必要もあります。
また、参考文献・引用文献選びにも気を配りましょう。特に、他者の研究結果については、最新の論文を引用しましょう。
さらに、完成した論文を提出する前に、プレ査読を依頼するのがおすすめです。
大学院生など、大学に所属している研究者であれば、指導教員などにプレ査読を頼むのもよいですし、研究所に所属しているなら、同僚に頼んでみましょう。
最後に、たとえ論文がリジェクトされてしまっても、査読者に対して適切かつ論理的に対応することで、再投稿率をアップさせることができます。
例えば、「先行研究との比較が不充分である」というコメントを受けたとしたら、以下のように回答するのがおすすめです。
ご指摘ありがとうございます。改訂版では、セクション2.3の議論を拡大し、関連研究との比較をより詳細に行いました。
このように、感情的にならず論理的に回答すること、「修正を反映した箇所」を明示して具体的に説明するのがポイントです。
査読者の意見に反対する場合も、以下のように、根拠を示しながら丁寧に反論しましょう。
査読者のご指摘に感謝します。ただし、XXの理由で本研究ではYYのアプローチを採用しました(p.5に説明を追記しました)。
まとめ
英語論文の書き方としては、まず論理的な構成を重視し、短く分かりやすい英文を意識するのがおすすめです。そして英語論文を書くからには、学術雑誌の査読を通ることを目指したいですよね。
英文の校正には便利なツールも多いですが、最終的には外部機関の校正を受けると間違いないでしょう。
さらに、仮にリジェクトされてしまった場合でも、査読者に対しては丁寧な返答を心がけましょう。
英語が話せるようになりたいけど、何から始めればいいかわからない…。
言語脳科学に基づいた実践型トレーニングを無料で体験できるチャンス!
✅ 学習満足度92%
✅ 3ヶ月でVERSANTスコア平均4.8アップ
✅ 東京大学と共同開発のメソッド
📍 無料体験でできること
✔ スピーキング力の無料診断であなたの英語力をチェック!
✔ 4つの英語ドリルが使い放題で弱点を徹底トレーニング
✔ 100種類以上の発音レッスン動画で発音を根本から改善
✔ ネイティブコーチとのレッスン1回で実践練習
今なら2週間無料トライアル実施中!
まずは気軽に試して、スピーキング力の変化を実感してください。 詳しくはこちら
詳しくはこちら

ホール 奈穂子
株式会社ギャビーアカデミー代表取締役
元九州大学職員。TOEIC 990、IELTS 7.5(Speaking 8.0)を誇る、英語学習独学のスペシャリスト。27歳から英語を学び直し、自らの人生で英語習得がもたらす可能性を証明。米国赴任、留学プログラムや海外大学との共同学位取得プログラムの設計・運営に携わった経験から、日本人の英語学習における課題を深く理解し、効果的な学習方法を追求。その集大成として、東京大学と共同で、脳科学に基づいた独自の英語スピーキング習得メソッドを開発。現在カナダ・バンクーバーに在住。世界を舞台に活躍する日本人ビジネスパーソンの育成に情熱を燃やし、日本とバンクーバーを往復しながら精力的に活動中。趣味はカナダを舞台にしたサケ釣り。