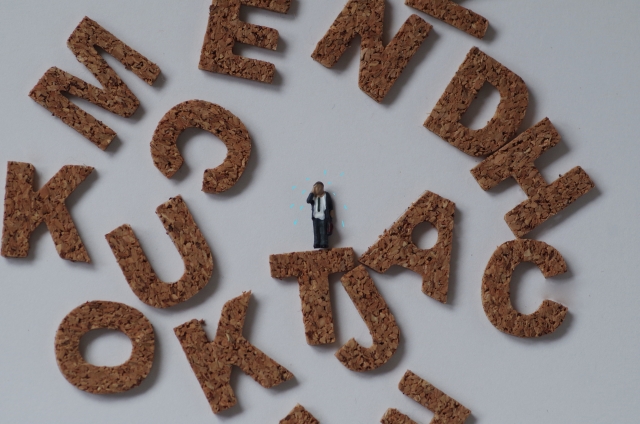国際的な探鉱プロジェクトでは、英語によるレポート作成を求められることも多いですよね。特に、投資家や海外のパートナー企業との情報共有を行う際、英語の探鉱レポートは重要なコミュニケーションツールとなります。ただ、いきなり探鉱レポートを英語で書く必要に迫られて、戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、英語圏でも通用する探鉱レポートで使う英語表現と、レポートの基本構成・正確さと説得力を高めるためのコツを紹介します。
探鉱レポートでよく使う用語の英語表現
まずは、探鉱レポートでよく使う用語を英語で何というか、おさえておきましょう。
以下の10個の表現をピックアップしました。
- 鉱化作用 mineralization
- 鉱脈 vein
- 含有量 grade / value
- 地質マッピング geological mapping
- 地表サンプリング surface sampling
- 試錐 drilling
- 掘削孔 drill hole
- 鉱徴・異常値 anomaly
- 断層・構造 fault / structure
- 指向性掘削 targeted drilling
「mineralization(鉱化作用)」は、動詞「mineralize(鉱化、ミネラル化)」の名詞形ですが、過去分詞形「mineralized」を使って、「mineralized zone(鉱化帯)」といった形でもよく使われます。
含有量は、単位とともに言及します。たとえば、金の含有量であれば、「2.3 g/t Au」のように表現します。
鉱徴や異常値を表す「anomaly」という単語は、身体や機能の不調を表す「abnonality(異常性)」という単語と混同しないようにしましょう。
「構造」は「structure」といい、「structural control(構造制御型)」という表現もよく使います。
そのほかにも、探鉱レポートでよく使う単語はたくさんありますが、次の章からの例文に織り込んでいくので、そちらも参考にしてください。
英語探鉱レポートの構成
それでは、英語で炭鉱レポートを書く際の構成を見ていきましょう。
英語圏で一般的に使われる探鉱レポートには、国際的な報告基準(例:NI 43-101, JORC Code)に準じた形式が多く使われます。
具体的には、以下のような流れです。
- 概要(Executive Summary)
- 序文(Introduction)
- 鉱区の説明と位置(Property Description and Location)
- 地質と鉱化の特徴(Geology and Mineralization)
- 探鉱手法(Exploration Methodology)
- 結果(Results)
- 解釈と考察(Interpretation and Discussion)
- 結論と提言(Conclusions and Recommendations)
- 参考文献(References)
- 付録(Appendices)
それぞれのセクションでどんなことを書けばいいのか、例文とともに見ていきましょう。
1. 概要(Executive Summary)
概要(Executive Summary)とは、レポート全体の要点を簡潔にまとめたものをいいます。
主な成果、例えば鉱化の兆候・資源量の初期推定・今後の展望などを述べ、読者が本文を読む前に大枠を把握できるようにする役割があります。
以下の例文を参考にしてください。
本レポートはXYZ鉱区での初期探鉱結果をまとめたものであり、表層サンプリングでは最大1.5g/tの金品位が確認された。さらなるボーリング調査が推奨される。
2. 序文(Introduction)
序文(Introduction)では、プロジェクトの背景や目的を説明します。
以下の例文を参考にしてください。
本レポートは、XYZ鉱区で実施された地質マッピング、サンプリング、および初期的な地質解釈を含む予備的探鉱作業の概要を示すものである。
このように序文には、作業時期や場所・方法・目的などを明記しましょう。
3. 鉱区の説明と位置(Property Description and Location)
序文を終えたら、いよいよ本文です。
本文ではまず、鉱区の場所について、地理座標・アクセス手段・近隣インフラなどを説明します。
所有権やリース状況などの法的背景もここで説明します。
地図・衛星画像・境界線の図などを挿入することも多いです。
具体的には、以下のような表現を使います。
XYZ鉱区はブリティッシュ・コロンビア州中部に位置し、約1,500ヘクタールにわたる有望な火山岩および堆積岩地帯を含む。
最寄りの町から砂利道を通じてアクセスでき、州の制度に則った鉱業権のもとに保有されている。
鉱区の説明と位置のセクションでは、以下の情報を含めると効果的です。
- 鉱区の地理的位置(どこにあるか、最寄りの町など)
- 面積と構成(何ヘクタール、いくつの鉱区で構成されているか)
- アクセス手段(どんな道で行けるか)
- 所有権と法的ステータス
- 地質的な注目ポイント
4. 地質と鉱化の特徴(Geology and Mineralization)
この項では、地質構造、岩石の質、鉱脈の配置などを説明します。地表および地下での鉱化の傾向やパターンも含めます。
場合によっては、他鉱区や地域との比較を加えることもあります。
それでは、具体的な例文を見ていきましょう。
鉱区は変質した火山岩に覆われ、石英-炭酸塩脈が見られる。金の鉱化は、黄鉄鉱および少量の黄銅鉱とよく関連している。
鉱化の様式は、近隣のABC鉱床で観察されるものと類似しており、共通の地質環境を示唆している。
このように、地質と鉱化の特徴を説明する項では、以下のような情報を含めましょう。
- 岩石の種類や地質単位
- 鉱化の形態や鉱物の特徴
- 鉱化の分布・傾向
5. 探鉱手法(Exploration Methodology)
探鉱レポートでは、探鉱手法についてもきちんと説明する必要がありますよね。
具体的な例文を見ていきましょう。
ボーリングはコア掘削機を使って実施された。採取した岩石試料は、記録・撮影・分割された後、金やその他の元素の分析を行う信頼できる検査機関に送られた。
試料は、調査ラインに沿って一定の間隔で採取された。結果の信頼性を確保するために、白紙試料、重複試料、標準試料を使った品質管理が行われた。
「実施する」は「carry out」、「採取する」は「collect」を使います。
ご自身の専門分野に合わせて、用語を置き換えて使ってみてください。
6. 結果(Results)
結果の項では、各手法で得られた主要な成果(分析値、掘削ログなど)を客観的に報告しましょう。
表・グラフ・断面図など、視覚資料で補足すると効果的です。
以下の例文を参考にしてください。
岩石試料から最大2.3g/tの金品位が得られ、地域内に鉱化石英脈が存在することが確認された。
土壌サンプリングにより、背景値を一貫して上回る金異常が300メートル以上にわたり確認された。
結果の項では、試料数や方法、分析結果の数値(g/t、含有量など)、どこで結果が出たか(地質構造や場所)に関する情報を含めましょう。鉱化の連続性など、意義のある解釈を含めると説得力がアップします。
必要に応じて表や図面を添えるのも効果的です。
7. 解釈と考察(Interpretation and Discussion)
結果を提示したら、その結果を地質的・経済的にどう読み解くか書きましょう。
この項は、レポート全体の説得力を高める要です。
事実のまとめだけでなく「だから次はこうするべき」というロジックを組み立てるようにしましょう。
金の鉱化は構造的に制御されている可能性が高く、地域の断層系との関連が示唆される。したがって、特定された構造傾向に沿った、さらなる掘削が求められる。
表層の地球化学的傾向は、地質構造と一致しており、構造制御を示している。鉱化の連続性を確認するため、指向性掘削が推奨される。
8. 結論と提言(Conclusions and Recommendations)
本文の最後は、探査成果の要約(何が確認できたか)で締めくくります。
さらに、次の段階で行うべき活動の提案など、投資判断・予算組みに影響するような、明確な提言ができるとよいでしょう。
今回の探査作業により、特に北西部のゾーンにおいて異常な金値を伴う石英–炭酸塩脈の存在が確認された。これらの結果は、有望な構造制御型の金システムを示唆している。
これを受け、第二段階の探査として、ピンポイントのダイヤモンド掘削および地表サンプリングの拡大を含む調査プログラムを推奨する。
このように、探査成果を分かりやすく要約するのはもちろんですが、プロジェクトが秘めている可能性や、次のステップの提案(掘削、掘削、地球物理探査、地質調査など)についても言及するとよいでしょう。
9. 参考文献(References)
探鉱レポートの末尾には、参考文献(References)と付録(Appendices)を添付します。
まず、参考文献の項には、地質文献や過去の報告書・使用したデータソースなどの一覧を記載します。
信頼性を担保するためにも、データソースの明記は重要ですよね。
記載方法は、学術的な引用スタイルに準じる場合もありますし、それぞれの業界の慣習に従う場合もあります。
たとえば学術論文であれば、以下のように記載するのが一般的です。
Bower, D., & Smith, J. (2015). “Geological controls on gold mineralization in the Stikine Terrane.” Canadian Journal of Earth Sciences, 52(4), 321–336.
政府・公的機関のレポートなどで、URLを記載する場合は、以下のように表記します。
Natural Resources Canada (2022). Mineral Exploration Activities Report. Available at: https://www.nrcan.gc.ca/
地質図やマップを提示する場合は、以下のような表記をします。
Geological Survey of Canada (1997). Geological Map of the Smithers Area (NTS 093L). Map 1890A, Scale 1:250,000.
文献は、発行者(著者や機関名)/年/タイトル/出典 の順で書くのが一般的です。
オンライン資料の場合は、 URLを明記しましょう。
一貫したフォーマット(ピリオドやイタリック体の使い方など)を守ると、よりプロフェッショナルな印象を演出することができます。
10. 付録(Appendices)
英語レポートには、付録(Appendices)を添付するのも一般的です。
採取データの詳細表、分析結果の原データ、図面類など、本文に入りきらないが検証のために必要な情報を、付録に掲載します。
ちなみに「Appendices」は「Appendix」という単語の複数形で、不規則変化をしています。
付録にいくつか項目がある場合は、「Appendix A, B…」と小見出しをつけましょう。
本文でも、「詳しくはAppendix Aを参照」などとリンクさせると効果的です。
表や図などを使って、読みやすいレイアウトになるよう工夫しましょう。
英語探鉱レポートで誤訳を防ぐコツ
英語探鉱レポートを、イチから自分の手で書くのは大変だと感じる方も多いと思います。
そこで活躍するのが、Google翻訳やDeepL翻訳などの翻訳ソフトでしょう。
ただ、翻訳ソフトは基本的に日本語を直訳してしまうので、こちらの意図がうまく伝わらなかったり、思わぬ誤解を生んだりする可能性があります。
この章では、英語探鉱レポートで誤解を防ぐポイントを紹介します。
- 受動態を多用しない
- 冠詞・数詞を正確に使う
- 日本語の直訳が誤解を招く例
- 日本語の曖昧表現が誤解を招く例
- 堅すぎる表現は避ける
受動態を多用しない
日本語のレポートでは、「成果が得られた」などと受動態が多用されますよね。
例えば、「鉱化が確認された」と言いたい時は、「Mineralization was confirmed.」などと言いがちです。
ただ、受動態には主語がないので、「誰が」「どうやって」といった情報がぼやけてしまい、充分に意図が伝わらず、説得力にも欠けます。
英語の探鉱レポートでは、積極的に能動態を選ぶようにしましょう。
例えば、以下のような言い方ができます。
私たちのチームは岩片サンプリングによって鉱化を確認した。
掘削結果は……を明確に示している。
冠詞・数詞を正確に使う
日本人には、英語の「冠詞」を重要視していない方も多いと思います。しかし、英語において冠詞は非常に重要なニュアンスを持つ単語です。
次の例文のペアを見てください。
南部ゾーンで複数の石英脈が確認された。
南部ゾーンで1つの石英脈が確認された。
例文1の場合、広い範囲、または複数地点でいくつもの石英脈が見つかったというニュアンスになります。
探鉱的には「ポテンシャルがありそう」と思わせる、より好意的・前向きな情報です。
それに対して例文2は、石英脈は見つかったが、現時点では1つのみで、探鉱の進捗としては「発見の初期段階」と受け取られます。
このように、冠詞や数詞の使い方ひとつで情報のニュアンスは大きく変わります。
まして、「A quartz veins were identified…」などと文法的誤りがあったりすると、英語圏の読者は非常に混乱してしまいます。
文法的誤りに対して過度に神経質になる必要はありませんが、「冠詞や数詞の使い方ひとつでニュアンスが変わる」という事実をおさえておきましょう。
日本語の直訳が誤解を招く例
翻訳ソフトなどが原因で、直訳した日本語が誤解を招くケースもあります。
たとえば、以前の章でも取り上げましたが、「異常値」は「abobomal value」と直訳されがちです。
ただ、「abnormal」は身体や機能の異常を表す言葉なので、探鉱レポートでは、「anormal」という単語を使いこなせるようにしておきましょう。
また、「鉱徴」という単語にも、「anomaly」を使うのが自然です。
翻訳ソフトを使うと、「mineral signs」「mineral indications」などの表現が散在してしまうので、最後は必ず人の目でチェックするようにしましょう。
日本語の曖昧表現が誤解を招く例
「対象エリア」「該当箇所」など、日本語の曖昧表現の訳出にも注意が必要です。
「該当箇所」を直訳すると「relevant area」となりますが、英語では「どこを指すか」が不明確と感じられてしまいます。
英語の探鉱レポートでは、以下のように明確な表現を使いましょう。
ABCターゲットゾーン内で……
プロジェクト地域の北部では……
堅すぎる表現は避ける
翻訳ソフトを使って「実施する」を直訳すると、「implement」や「execute」などと訳出されるかもしれません。
しかし、「implement」は行政文書のようですし、「execute」は軍事的・法的なニュアンスがあって、いずれも堅すぎる表現です。
英語でレポートを書く際は、何よりも「分かりやすさ」が重要視されます。
「実施する」と言いたい場合は、「carry out」や「conduct」などの表現が好まれます。
「サンプリングを実施する」という場合は、「動詞+samples」より、「collect samples(サンプルを集める)」という表現を使うとよいでしょう。
「使用する」「利用する」も「utilyze」と訳されることが多いですが、単に「use」を使った方が分かりやすくなります。
まとめ
英語で探鉱レポートを書く際には、専門的な内容を分かりやすく、かつ正確に伝える必要があります。
日本語のレポートを翻訳ソフトで直訳しただけだと、受動態が多かったり、堅すぎる表現が多かったりして、誤解を生んでしまうかもしれません。
必ず最後は自分の目でチェックして、適切な英語表現を選ぶようにしてください。
英語が話せるようになりたいけど、何から始めればいいかわからない…。
言語脳科学に基づいた実践型トレーニングを無料で体験できるチャンス!
✅ 学習満足度92%
✅ 3ヶ月でVERSANTスコア平均4.8アップ
✅ 東京大学と共同開発のメソッド
📍 無料体験でできること
✔ スピーキング力の無料診断であなたの英語力をチェック!
✔ 4つの英語ドリルが使い放題で弱点を徹底トレーニング
✔ 100種類以上の発音レッスン動画で発音を根本から改善
✔ ネイティブコーチとのレッスン1回で実践練習
今なら2週間無料トライアル実施中!
まずは気軽に試して、スピーキング力の変化を実感してください。 詳しくはこちら
詳しくはこちら

ホール 奈穂子
株式会社ギャビーアカデミー代表取締役
元九州大学職員。TOEIC 990、IELTS 7.5(Speaking 8.0)を誇る、英語学習独学のスペシャリスト。27歳から英語を学び直し、自らの人生で英語習得がもたらす可能性を証明。米国赴任、留学プログラムや海外大学との共同学位取得プログラムの設計・運営に携わった経験から、日本人の英語学習における課題を深く理解し、効果的な学習方法を追求。その集大成として、東京大学と共同で、脳科学に基づいた独自の英語スピーキング習得メソッドを開発。現在カナダ・バンクーバーに在住。世界を舞台に活躍する日本人ビジネスパーソンの育成に情熱を燃やし、日本とバンクーバーを往復しながら精力的に活動中。趣味はカナダを舞台にしたサケ釣り。